2024年2月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
2024年2月20日
19日月曜は友人やフォロワーさんと通話したりしてたな。一日中雨だったから家に籠っていた。デジタル色塗り分からんと呻いてた記憶。
一週間雨だと覚悟を決めていたが、晴れ間が覗いたので洗濯物が干せて嬉しかった。一週間以内に切れそうだった子のオムツも買いに行けた。サボりたかったけど雨の日多そうだから、何とか気力を出した。
今週は、天気予報を見る限り雨がちだが、いわゆる菜種梅雨というやつだろうか。
離乳食時、私の手からではなく、皿からスプーンを持っていって食べられるようになった。スプーンで食べ物をすくうことはまだできないけれど、ちょっとした進歩。
一週間雨だと覚悟を決めていたが、晴れ間が覗いたので洗濯物が干せて嬉しかった。一週間以内に切れそうだった子のオムツも買いに行けた。サボりたかったけど雨の日多そうだから、何とか気力を出した。
今週は、天気予報を見る限り雨がちだが、いわゆる菜種梅雨というやつだろうか。
離乳食時、私の手からではなく、皿からスプーンを持っていって食べられるようになった。スプーンで食べ物をすくうことはまだできないけれど、ちょっとした進歩。
2024年2月18日
かびちゃんずめでたい
起床後、買い物と育児を夫と手分けして片付け、昼は中華を食べに行った。
午後ACL観戦しながらお絵描きをした。夜ご飯は鍋。
起床後、買い物と育児を夫と手分けして片付け、昼は中華を食べに行った。
午後ACL観戦しながらお絵描きをした。夜ご飯は鍋。
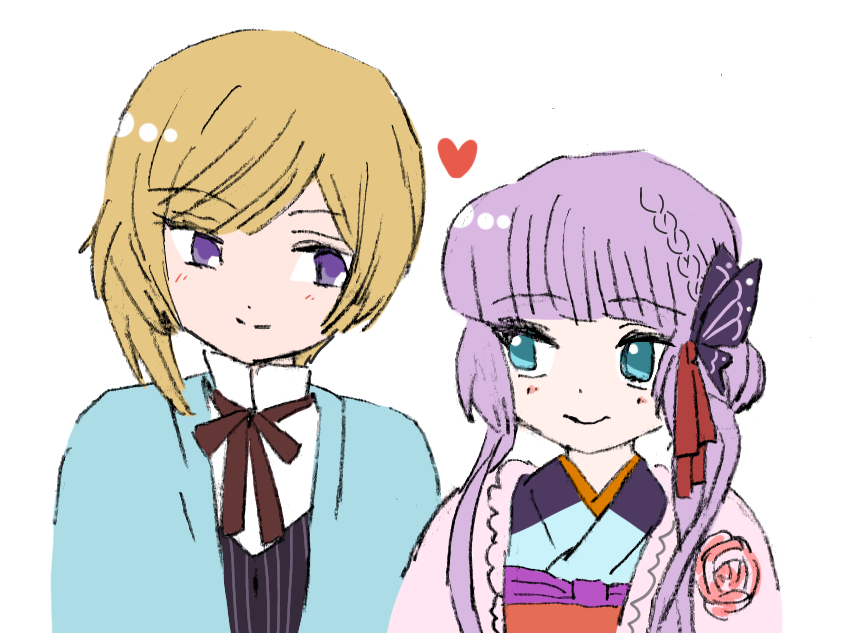
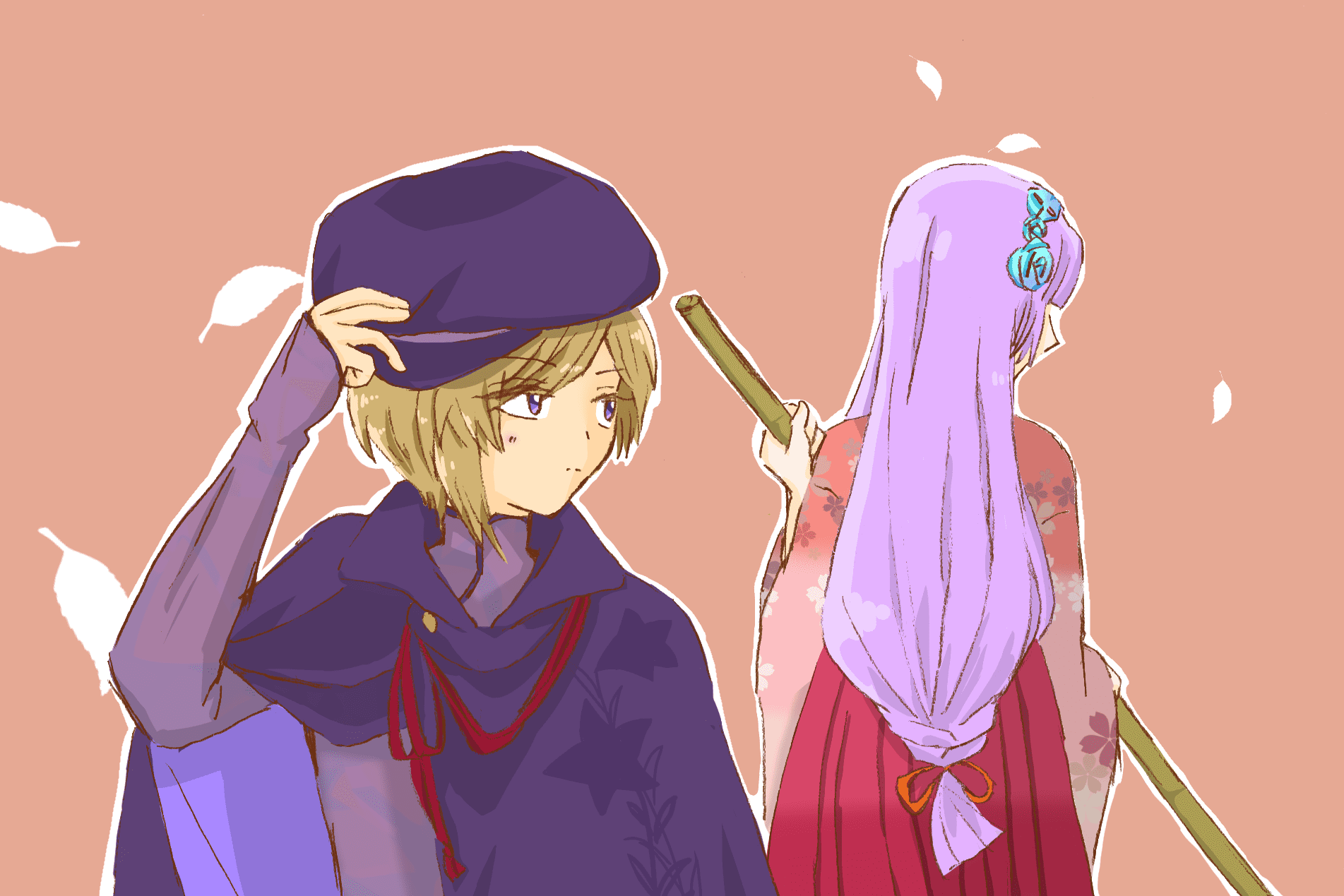
アダムしんどい以上にルカがケアされていなかったことに私は怒ってるのだと思う。
ジャンルが乙女ゲーム(多分)なぶん、ルカのことより「アダムしんどい」が前面に立ってる感じを受けた。それが余計に受け入れがたかったのかも。
そして私は自己防衛以外の殺人に厳しいのかもしれない……隠してしまったぶん、より情状酌量の余地なくないか?と思ってるふしがある(諸悪の根元はゾラですが……)
これはアダムに限らずシュウに対しても。
※月影猪口依存は好きだけどそれはそれとして情状酌量の余地なしと思ってるしそういう描かれ方なので受け入れられた
バスタフェで描かれる社会の汚さ・信用ならなさに疲れてしまった……という感想をfusetterに書いたけど、
リンボたちもまた、その信用ならない社会に甘んじた上で、強者として金稼いでる印象を受けてしまい、彼らやテウタに気持ちを乗せることができなかったというのが、バスタフェに対する総括かもしれない。
吐き出すほうが繰り返し考えない気がするので、この際書き出すと、時間遡行能力に対するテウタのスタンスもあまり得心が行かないまま真相を迎えてしまった。ただ、真相の内容が内容なので、皮肉な能力だな……とも今は思っている。
そもそも「何が正義かは自分が決める」という言葉が、『何が正か悪か決めづらい時代だが、それでも自分の外側に他者と共有すべき倫理は在るのではないか。少なくともその在る無しから他者と話し合い、模索し、葛藤し続けるべきではないか』と考える“私”とぶつかってしまったので、ホントにこれはライターとの思想的対立としかいいようがないのだろう。
私、近代社会において殺人はアウトだと思うから。畳む